
朝は大騒ぎ、夜は寝かしつけに一苦労。子供がなかなか寝ないし、朝も起きられない…あなたの家でもそんな毎日が続いていませんか?
「うちの子だけかも…」と不安になったり、「何度言っても直らない」とつい怒ってしまったり。親のストレスもどんどんたまっていきますよね。
でも安心してください。この記事では、小学五年生でもすぐに実践できる「早寝早起きの習慣づけ」の方法を、わかりやすく紹介します。
たった1週間で、「夜は自分から寝る」「朝はすっきり起きる」子供に変わった家庭もたくさんあります。親子の会話も増えて、朝の時間がもっと楽しくなりますよ!
この記事は、子育ての基本となる生活習慣の整え方を、科学的知見や実際の家庭の声に基づいて丁寧に解説しています。
まずは、次の章から読んで、できそうなことを今日から1つ始めてみましょう!
なぜ子供に早寝早起きが必要なの?親が知っておくべき基礎知識
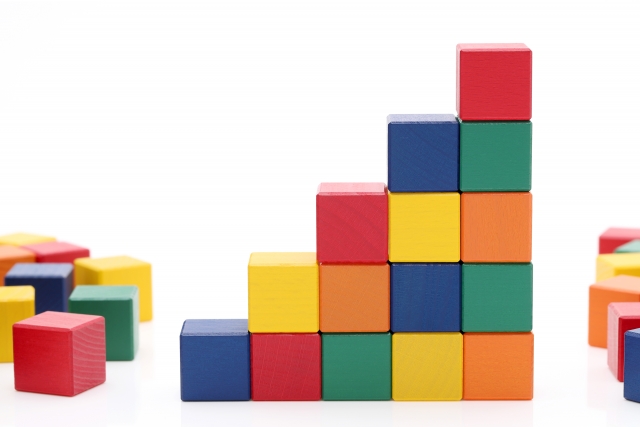
子供の心と体の健康には、毎日の「早寝早起き」がとても大切です。
なぜなら、夜にしっかり眠ることで、脳と体がリフレッシュされ、次の日に元気いっぱい動けるからです。特に成長期の子供にとって、睡眠は身長や記憶力、感情のコントロールにも関係しています。
例えば、毎晩夜更かししていた子が、早く寝るようになっただけで、朝ごはんを残さなくなり、学校でも集中できるようになったという話もあります。
つまり、ただの「生活のルール」ではなく、健康と学びの土台なのです。
だからこそ、まずは「なぜ早寝早起きが大切なのか」を親が理解して、家庭で意識していくことがとても重要です。
あなたの子供も当てはまる?こんな習慣が早寝早起きを邪魔している

子供が早寝早起きできないのは、子供のせいではなく、日々の習慣に原因があるかもしれません。
多くの場合、寝る直前までテレビやゲームをしていると、脳が興奮して眠りにくくなります。また、寝る部屋がうるさかったり明るかったりしても、睡眠の質が下がってしまいます。
例えば、ある家庭では、リビングで寝落ちするのが習慣になっていて、夜中に起きて寝室に移動するため、眠りが浅くなっていました。
これを、決まった時間に寝室に行くように変えただけで、朝の機嫌が見違えるほど良くなったのです。
このように、少しの工夫で子供の睡眠習慣はぐっと改善します。まずは、家の中で「眠りを邪魔しているもの」がないか見直してみましょう。
子供が自然に早寝早起きしたくなる!親ができる7つの習慣術

子供に早寝早起きを身につけさせるには、親が生活の中でちょっとした工夫をすることがポイントです。
ただ「早く寝なさい」「起きなさい」と言っても、子供はなかなか行動に移せません。習慣化には、楽しくて続けられる工夫が必要なんです。
① 就寝・起床時間を「見える化」する
壁にタイムスケジュールを貼ることで、目に見えて行動しやすくなります。子供は「今何時に何をするか」がわかると安心して行動します。
② 夜の過ごし方ルーティンをつくる
例えば、「ごはん→おふろ→絵本→寝る」といった流れを毎日同じ順番にするだけで、体が自然に「そろそろ寝る時間だな」と反応します。
③ スクリーンタイムを1時間前に終了
寝る前のスマホやテレビは、目や脳を刺激して眠気を遠ざけます。代わりに静かな音楽や読書に切り替えると、寝付きが良くなります。
④ 寝室を“快眠仕様”に整える
カーテンで光を遮ったり、ぬいぐるみを置いたりして安心感を与えることで、子供の睡眠の質がアップします。
⑤ 休日も同じ起床時間をキープ
土日だけ遅く起きると体内時計がズレます。休みの日もいつも通り起きて、昼寝などで調整しましょう。
⑥ 朝時間を楽しみにする工夫
子供が「起きたら楽しいことがある!」と感じると、起きるのが苦じゃなくなります。例えば、朝食に好きなメニューを入れるなどです。
⑦ 親も一緒に生活リズムを整える
子供は親の真似をします。まずは親自身が早寝早起きを意識して行動することが、最大の教育になります。
小さなことからでも良いので、まず1つだけ習慣を取り入れてみましょう。続けることで、自然と体が「朝型」に変わっていきます。
実例紹介:早寝早起きに成功した家庭のリアル体験談

実際に早寝早起きを成功させた家庭の体験談には、ヒントがたくさん詰まっています。
他の人の成功体験を知ると、「自分の家庭にもできるかも!」という気持ちになれます。具体的なやり方を参考にすることで、より効果的に実践できます。
📘 小学生の女の子とお母さんの例
この家庭では、夜9時に寝ることを目標にし、「おやすみタイマー」を使って毎晩のルーティンを定着させました。1週間後には、タイマーが鳴る前に自分から「そろそろ寝るね」と言うように!
📘 3兄弟を育てる家庭の例
にぎやかで寝かしつけに苦労していたお父さんとお母さんは、「寝る前のダンスタイム→絵本→おやすみクイズ」という楽しいルールを作りました。3人とも「次の夜も早く寝たい」と言うようになり、親の負担も激減。
どの家庭も、最初から完璧だったわけではありません。小さなことからコツコツと、親子で一緒に取り組むことが成功のカギです。
よくある質問(FAQ)

ここでは、早寝早起きに関してよくある疑問をわかりやすく答えます。
どんなにやる気があっても、疑問があると前に進めません。ここでしっかりクリアにしましょう。
Q1:何時に寝かせれば良い?年齢ごとの目安は?
A:小学生なら21時までに寝るのが理想です。7〜9時間の睡眠が必要なので、朝6時に起きるなら21時就寝を目指しましょう。
Q2:子供が寝たがらない時はどうすれば?
A:寝る前にリラックスできる環境をつくりましょう。静かな音楽や絵本、ぬいぐるみなどがおすすめです。
Q3:塾や習い事で帰りが遅い場合は?
A:夜遅くなった日は、次の日の起床時間を少しだけ遅らせたり、お昼寝を取り入れるなどして調整しましょう。
Q4:朝どうしても起きない子に有効な声かけは?
A:「早く起きなさい!」ではなく、「今日は楽しみだね!」などワクワクする声かけが効果的です。
Q5:共働きで夜が忙しいときは?
A:夜のルーティンを短くまとめ、「お風呂と絵本だけ」などにすると時間が足りなくても早寝が可能です。
疑問が解決すると、親も自信を持って取り組めます。迷った時は、まずは「できることからやってみる」が大事です。
まとめ|「早寝早起き」は子供の未来を育てる最強の習慣

早寝早起きは、子供の健康・学習・心の安定を支える「土台」です。
日々の小さな習慣が積み重なることで、大きな変化が生まれます。体の成長にも、心の落ち着きにも、良い影響が表れます。
毎晩同じ時間に寝ることで、次の日の朝がすっきり。朝ごはんもちゃんと食べられて、学校でも元気に過ごせるようになります。何より、親子の会話が自然に増えるのも嬉しいポイントです。
今日からでも始められます。「まず1つ試してみる」ことが、成功への第一歩です。親子で楽しみながら、明るい毎日をつくっていきましょう!

